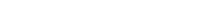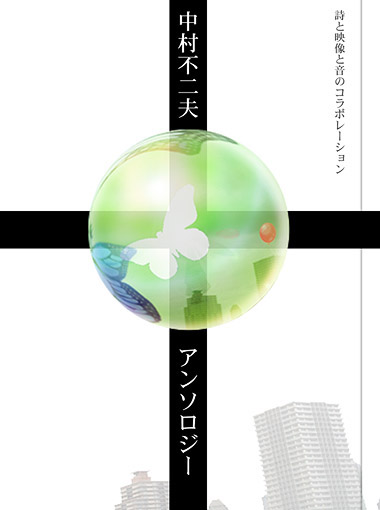ものの遠さを埋めようとする生の営みは、それが遠いものに導かれる歩みである限り自己矛盾を免れぬことだろう。氏の詩篇に貫いて感じられるのはそういった分裂に対する切実な反省である。だが嫌悪ではなくて、運ぶ足を踏みしめ踏みしめ、詩人は坂を登り続ける。
戦後の経済成長はいわば商人たちが小賢しさを身につけることで到達し得た高みである、と言えるかもしれない。彼らは詩人の影であるが、その彼らとともに浮沈を見て、同時代を生きた詩人の言葉が、しかし暗さに留まらないのは、なお生きる身近なひとびとへの日常的な信頼が、地に足のついたものであるからだろうと思う。(菅野 充・編集者)

電子ブック詩集/タイプ
- 個人詩集
- ● ポエムービー(動画)編
- ● テキスト(文字中心)編
- シリーズ(テキスト編)
- 100人の詩人・
100冊の詩集EX.
EX.シリーズは『100人の詩人・100冊の詩集』の「電子ブック(テキスト編)」バージョンです!
アマゾンの Kindleストア、アップルの「iBookstore」でもご購入いただけます。
* アップルのiBookstoreに接続するにはiPad、iPhoneなどのiOSデバイス、またはMacが必要になります。

本の詩集/カテゴリー
- 新刊詩集
- 受賞詩集
- 個人詩集/詩論
- シリーズ
- 受賞詩集
- ● 現代詩の50人
- ● 新/詩論・エッセイ文庫
- ● 新・日本現代詩文庫
- ● 新・世界現代詩文庫
- ● 叢書■現代の叙情
- ● Critic & Creation
- ● 100人の詩人・
100冊の詩集 第II期- ● 100人の詩人・
100冊の詩集- ● 40周年記念新詩集
- ● 現代詩の新鋭
- ● 叢書(社会 現実/変革)
- ● エリア・ポエジア叢書
- ● 詩と思想新人賞叢書
- ● 詩と思想詩人集
- 21世紀詩人叢書@
- 21世紀詩人叢書 Ⅱ@
- 叢書新世代の詩人たち@
- 現代詩人論叢書1-13@
- 現代詩の前線1-15@
- 現代中国の詩人@
- ● 新/詩論・エッセイ文庫
- 文庫
- ● 新・日本現代詩文庫
- ● 新・世界現代詩文庫
- 日本現代詩文庫 第1期@
- 日本現代詩文庫 第2期@
- 世界現代詩文庫@
- 新・世界現代詩文庫@
- 詩論・エッセイ文庫@
- 新|詩論・エッセイ文庫@
- ● 新・世界現代詩文庫
「@」の付いたカテゴリーは現在Eメールにてご注文を受付中。順次、カート方式に更新してまいります。