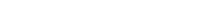一昨年末に、「来年こそパソコンを開始します」とか宣言していたのもうなずける。電子詩集を出しておいて、作者自身が読めないというのでは都合が悪かろう。そのIT化戦略も軌道に乗ったらしく、この頃はメールなど頂くようになった。よれよれの万年筆文字のつまった葉書をもらえなくなるのかと思うと寂しい気もするが。
『歌と彷徨1』は5冊の詩集から選んだ12編の詩からなる。その中でも特に5編と多いのが『アイオワ冬物語』からで、今回この詩人の不思議な立ち位置を実感した。"路上派" 詩人のスターで、アメリカとジャズとビートが好きな詩人と漠然と思っていたが、ことはそんなに単純ではないようだ。雨の国の日本からくる手紙はいつも濡れていて、縦書きで書かれた詩は雨のようだ(「アイオワの風に吹かれていると」)と言いながら、そこから抜け切れない中上哲夫というジャパニーズ詩人がいて、案外アメリカにあって孤独なのだった。
『歌と彷徨2』は高見順賞と丸山薫賞のダブル受賞となった『エルヴィスが死んだ日の夜』から10編を収録したもの。カラフルなアメリカのイメージとは違って、(誰かがレビューで書かれていたが)案外モノトーンなのだった。ビートが古典になるということなのだろうか。ジャズやプレスリーが背後に流れている。しかし、プレスリーがある日死ぬように、時代は流れていく。ある日常の中でヴィヴィッドだったものがある日古典となるように。しかし古典になることは死ぬことではなく、異なるヴィヴィッドな力が容器に満たされた瞬間かもしれない。すぐれたものはみなもともとそうなのだ。
動画あり、音楽あり、字が蛇行したり雨のように落ちてきたり、従来の詩の鑑賞とは違う面白さがある。二冊とも朗読は全て作者が行なっている。絶叫などどこにもない。静かで訥々としている。私が二十代で聞いた時もそうだったが、あの頃はそれがつまらなく思えた。60歳を過ぎて、その価値に目覚めた。歳はとるものだ。
『歌と彷徨2』にも入っているが、私のとても好きな詩をご紹介する。文字だけで。詩を書くことの孤独と、理由のわからぬ幸福感がそこにある。飲み会から別れる時に「さあ、帰って詩でも書こう」というのが中上さんの有名な口癖で、みんなが冗談だと思っていたが、辻征夫があれは本当だった、と書いているという。その話とこの詩の情景が重なってしまうのだ。
未明に訪れる者よ 中上哲夫
詩を書くことに疲れてベッドに横になろうとする時刻、枯葉を踏む音がまっしぐらに近づいてくるのだ。男の家に向かって。はるか遠方から。
そして書斎の窓から大きな頭部を差し入れると、机の上の書きかけの詩稿を読み始めるのだ。熱心に。かれはそのために遠い道のりをやってくるのだ。夜ごと夜ごと。そうして、読み終えると、ふたたび帰っていくのだ。森の奥へ。
詩を書くたびに、男はいつもすこしかなしくなるのだった。いくら書き続けてもけして読まれることがないのだと思うと。でも、と男はしあわせな気持ちで思い返すのだ。いま、わたしには読者がいるのだと。世界でただ一人の大きな頭の読者が。
この朝、男は書きかけの詩稿の上に顔をふせたままぐっすりねむり込んでしまった。昼間の疲れで。しかし、かれは男が目覚めるのをじっと待つのだった。窓のそとで。しかし、金星が東の空に消える前に、ひっそりと帰っていった。森の奥へ。
かれは何者なのか。男にはいっさい不明だ。その姿を一度も見たことがないので。ただその存在を確かに感じることができるだけなのだ。詩稿のしみと、あとに残された強烈な体臭とによって。
(このレビューは、投稿者がmixiの日記に書かれたものですが、ご本人の承諾を得て管理者が転載させていただきました。)

電子ブック詩集/タイプ
- 個人詩集
- ● ポエムービー(動画)編
- ● テキスト(文字中心)編
- シリーズ(テキスト編)
- 100人の詩人・
100冊の詩集EX.
EX.シリーズは『100人の詩人・100冊の詩集』の「電子ブック(テキスト編)」バージョンです!
アマゾンの Kindleストア、アップルの「iBookstore」でもご購入いただけます。
* アップルのiBookstoreに接続するにはiPad、iPhoneなどのiOSデバイス、またはMacが必要になります。

第33回「詩と思想」新人賞
授賞式
授賞式
本の詩集/カテゴリー
- 新刊詩集
- 受賞詩集
- 個人詩集/詩論
- シリーズ
- ● 現代詩の50人
- ● 新/詩論・エッセイ文庫
- ● 新・日本現代詩文庫
- ● 新・世界現代詩文庫
- ● 叢書■現代の叙情
- ● Critic & Creation
- ● 100人の詩人・
100冊の詩集 第II期 - ● 100人の詩人・
100冊の詩集 - ● 40周年記念新詩集
- ● 現代詩の新鋭
- ● 叢書(社会 現実/変革)
- ● エリア・ポエジア叢書
- ● 詩と思想新人賞叢書
- ● 詩と思想詩人集
- 21世紀詩人叢書@
- 21世紀詩人叢書 Ⅱ@
- 叢書新世代の詩人たち@
- 現代詩人論叢書1-13@
- 現代詩の前線1-15@
- 現代中国の詩人@
- 文庫
- ● 新・日本現代詩文庫
- ● 新・世界現代詩文庫
- 日本現代詩文庫 第1期@
- 日本現代詩文庫 第2期@
- 世界現代詩文庫@
- 新・世界現代詩文庫@
- 詩論・エッセイ文庫@
- 新|詩論・エッセイ文庫@
「@」の付いたカテゴリーは現在Eメールにてご注文を受付中。順次、カート方式に更新してまいります。